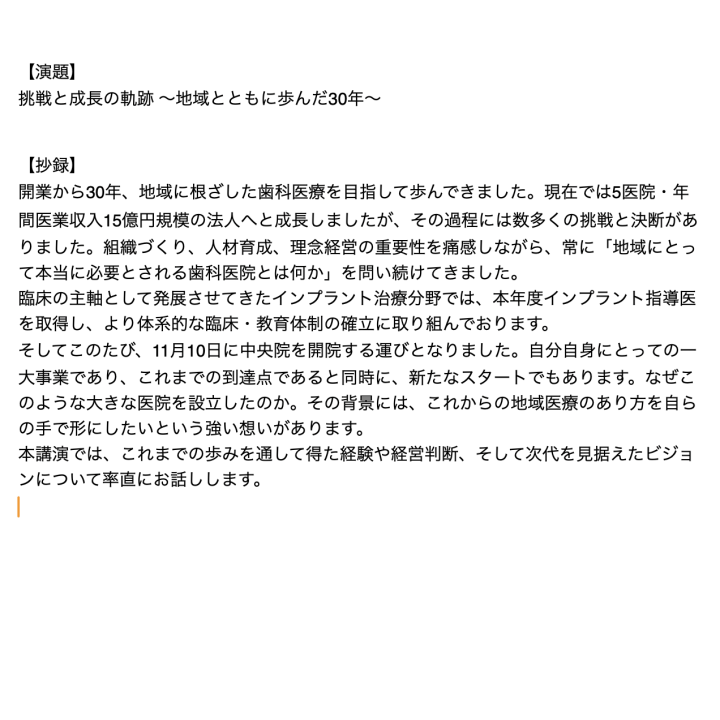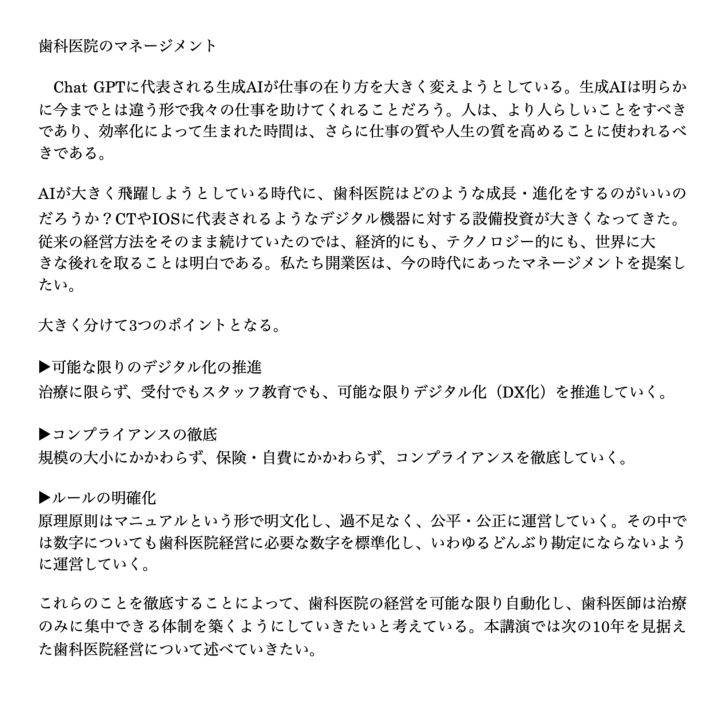2025年9月7日 脇宗弘先生 特別講演会(終了)
演題 患者のための接着修復治療という選択肢
~コンポジットレジン・ジルコニア・CAD/CAM冠を臨床で用いるにあたって~
近年、患者の修復治療に対する審美的要求度が高まってきただけでなく、低侵襲な術式を望まれる声も多くなってきたことを実感する。その背景としてはMIコンセプトでメタルフリーな治療を具現化できる時代であると患者側に認識させるだけの情報がwebでは溢れているからに他ならない。
MIコンセプトに基づく接着修復治療は、従来から行われている金属を用いた物理的嵌合と合着に頼った修復治療とは大きく異なる。
特に健全残存歯質に対する削除量には歴然の差がみられる。
このことは、当該歯における治療後の予知性に大きく関係すると考える。
しかしながら最終修復物装着時の接着操作は、最終修復物の材料と支台歯の条件に合わせた歯面処理を必要とされるためにテクニックセンシティブでありテクニカルエラーによる失敗を起こしやすいのも事実である。本講演では、自らの臨床例を用いて基本的な接着修復治療に対する考え方やチェアーサイドでの勘所をお伝えしたい。
経歴
1965年 大阪市生まれ
1990年 大阪歯科大学卒業
1992年 大阪市阿倍野区にて脇歯科医院開設
日本臨床歯科医学会 会員 京都支部相談役
K-project 会員
阿倍野区学校歯科医会 副会長
モリタ実践歯科臨床プラクティスコース インストラクター
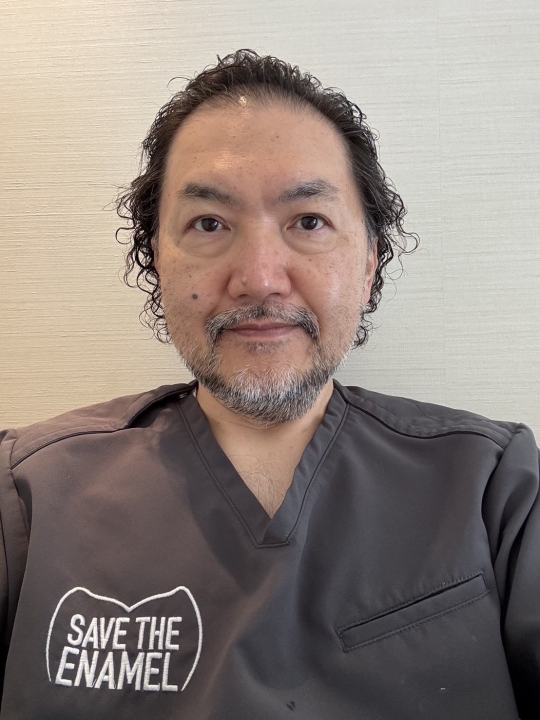
2025年2月9日 中原維浩先生特別講演会(終了)
そして、物販については担当者を特に設けるのではなく、全員経営、全員担当の心持ちで推進する必要があるとお話しされました。
NPO法人 口腔がん早期発見システム全国ネットワーク
日本病巣疾患研究会(JFIR)
2024年12月15日 荒井昌海先生特別講演会(終了)
熊本歯科三水会では、経営と学術を高次元に融合しその両面から歯科界を牽引するMID-G最高顧問 荒井昌海先生を招聘し、特別講演会を開催しました。
講演会はシンギュラリティの話題からスタートしました。
デジタル化の波がどのような影響を生むのか?
よく『AIが人間から仕事を奪う』という話があるが、
そうではなく『AIを使う人間が、AIを使わない人間の仕事を奪う』時代になるという。
実際に荒井先生の歯科医院グループで、分業化をデジタルにて省力化を進めたところ、財政面でのメリットもさることながら、人事面の様々な変化による気づきが生じたと
話があった。元々荒井先生の率いるエムズグループの開業はエビデンスに基づき100名の社員から開設した医院であった。しかしながら、組織の成長に伴い150名を超えると、その組織は瓦解するという理論を知りながら、組織の成長に伴いうっかり170名になった時点で、組織の意思疎通に以前のような一体感がなくなったことを肌で感じ、社員を150名にすぐに戻したところ、再び一体感を取り戻すことができたというエピソードは大変興味深い話であった。
9つの医院の電話受付を1つのコールセンター3名で行う話、医院のスクラブ等洗濯物の回収補充物の管理等の担当部署、そして配送の費用等細かな解説があった。
勤務医を新たに採用する際の見学時には、医院の治療内容を見学してもらうときに、○○○○○を必ず装○の上で治療しているところを見せると、内定に繋がりやすいとのこと。
午後の部はデジタル化におけるiOSの世代変化と、医院の設備が具備すべきWi-Fi設備の解説があった。次に、ジルコニアの基礎的な解説と今後の展開について話があり、その後、熊本では中々見ることのない、他院All on 4の上部構造破折症例の光学印象による上部構造作成をオーストラリアとのやり取りで完成した症例提示、また、別症例でAll on 4支台インプラントの1本が骨吸収を起こしたケースに対し、十分な肉芽組織除去とリグロス+新インプラントの使用により、骨組織の回復安定を図った症例の解説があった。
最後に歯科医院経営における損益分岐の考え方と、M&Aにて医院売却を有利にするための
医院財務のあり方の解説がなされた。
前日の懇親会から、大変内容充実で濃厚な話題、講演に会員一同圧倒されました。
荒井昌海先生
東京医科歯科大学 卒業
同大学院 修了
エムズ歯科クリニック開院
日本口腔インプラント学会指導医
EAO認定医
大阪歯科大学客員教授
東京医科歯科大学非常勤講師
MID-G最高顧問
2024年8月4日 増田英人先生特別講演会(終了)
午前10時開始でまず、インプラント治療よりも天然歯を残すことを特に情熱を持って取り組んでいるとの話からでした。その後、インプラント治療におけるGBRの難易度の解説がなされ、膜の露出への対処法として、非吸収性膜は3ヶ月で撤去、吸収性膜は消毒を繰り返すことのみと、実際の症例写真を用いて解説された。手術の際、特にフラップの減張切開について、メスの腹を用いて、繊維をほぐし、剥離子で伸ばしていく様を動画を交え丁寧にご教授された。ソーセージテクニックにおいては、舌側に位置する膜の隅角のタックピンで止めさらに遠心頬側隅角をピンで止めた後、膜を伸ばしながら補填材を膜下に十二分に添入することが重要とのこと。(膜は伸びるBioMendを使用する。)下顎の垂直GBRは下顎枝があるので、上顎よりは難易度が若干低いこと、また、上顎の垂直GBR成功のためには、上顎結節部の骨があることが、必須と解説された。
午後の部においては、抜歯即時インプラントの優位性と、上顎結節部の結合組織ならびに骨移植により、審美領域の骨の水平的吸収を防ぐ新たな手法について、解説がなされた。
6時間に及ぶ講演と質疑応答、長時間を感じさせない極めて濃厚な学びの時間でした。
増田英人(Masuda Hideto)先生
御略歴
2001年 広島大学歯学部卒業
2008年 ますだ歯科医院開業
2011年 医療法人ライフスマイル設立
2023年 大阪ENの会 会長就任
ICOI指導医・認定医
ITIフェロー
2024年2月18日日曜日 中村社綱先生特別講演会(終了)
熊本市、および天草市にてご開業の中村社綱先生を招聘し、
『歯科治療におけるデジタルソリューションのススメ』
とのタイトルにて特別講演会を開催いたしました。
当日は、熊本城マラソンの開催日にもかかわらず
15名の会員が参加し、午前の部はインプラントの歴史、午後の部はデジタルソリューションを
ご講演いただき、ゾーン1、ゾーン2を戦略的に活用するインプラント術、99%成功するインプラント手術の術式等につき、膨大なエビデンスに
基づく発表がなされ、会員一同聴き入りました。
中村社綱(なかむらたかつな)先生
御略歴
1975年 神奈川歯科大学卒業
1975年 九州大学歯学部口腔外科学教室入局
1980年 中村歯科医院開業(熊本県本渡市※現 天草市)
1998年 インプラントセンター・九州開設(熊本県熊本市)
元 九州大学医学部臨床教授
元 島根大学医学部臨床教授
熊本大学医学部臨床教授
神奈川歯科大学客員教授
デンタルコンセプト21最高顧問